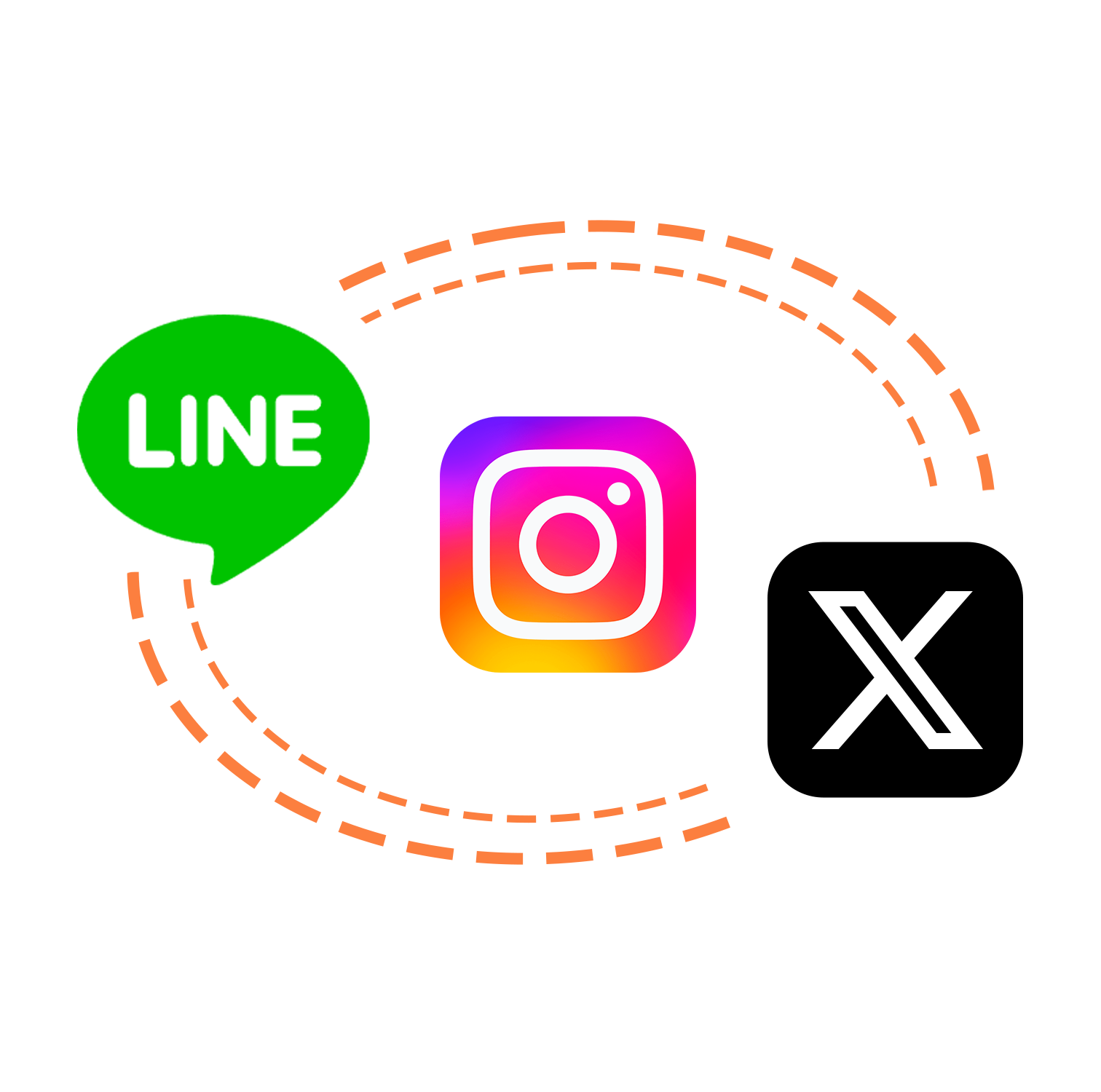PETTENA編集部は、ペットとその飼い主がより良い生活を送れるよう、専門的な知識に基づいた信頼性のある情報を提供するチームです。特に、ペットカートを中心に、安全で楽しいお出かけをサポートするコンテンツをお届けしています。
犬のレプトスピラ症とは?症状・原因・予防法をわかりやすく解説!|ぺテナ
目次をすべて表示
「レプトスピラ症」という病気をご存じですか?犬が感染すると腎臓や肝臓に深刻な影響を及ぼし、最悪の場合、命に関わることもあります。さらに、人にも感染する可能性があるため、飼い主さんにとっても注意が必要です。本記事では、レプトスピラ症の症状や原因、予防法までわかりやすく解説します。愛犬を守るために、ぜひ最後までご覧ください!
犬のレプトスピラ症とは?
レプトスピラ症の概要
レプトスピラ症は細菌感染症の一種で、人畜共通感染症として知られています。レプトスピラ菌が原因で発症し、感染した犬は発熱、嘔吐、腎不全、肝障害などの症状を引き起こし、重症化すると命に関わることもあります。特に、川や池、水たまりなどの汚染された水や、感染動物の尿を介して感染するリスクがあるため、飼い主は注意が必要です。
日本国内での発生状況
日本国内では、温暖で湿度の高い地域を中心に犬のレプトスピラ症の発生が報告されています。特に沖縄や九州地方では感染リスクが高く、大雨や台風の後に発生が増える傾向があります。また、関東や関西の都市部でもネズミを媒介とした感染例が確認されています。
近年では、河川や公園の水たまりで感染したケースもあり、アウトドアや水遊びの際には注意が必要です。

犬のレプトスピラ症の原因と感染経路
レプトスピラ菌の特徴とは?
レプトスピラ菌は、細長いらせん状の形をした細菌で、動物の尿などを介して水や土壌に広がります。特に犬に影響を与えるのは「カニコーラ型」「イクテロヘモラジー型」「オータムナリス型」などの血清型で、これらは腎臓や肝臓に深刻なダメージを与えることがあります。レプトスピラ菌は湿気の多い環境を好み、川や池、水たまりなどの水辺に多く存在します。
犬はどこで感染する?主な感染経路
- 汚染された水や土壌
犬が川や池、水たまりで遊んだり、ぬかるみを歩いたりする際、レプトスピラ菌が付着した水を飲んだり、体に触れたりすることで感染することがあります。特に雨が多い季節は、菌が繁殖しやすくリスクが高まります。
- 感染した動物の尿との接触
ネズミや他の犬の尿に含まれるレプトスピラ菌が地面や水たまりに残り、それに触れた犬が感染することがあります。都市部でもネズミが多い場所では注意が必要です。
- 傷口や粘膜を通じて感染
目や口の粘膜、皮膚の小さな傷からもレプトスピラ菌が侵入し、感染することがあります。散歩中に汚れた水に触れた後、顔を舐めることで感染リスクが高まるため、帰宅後の足や体の拭き取りが大切です。

犬のレプトスピラ症の症状と重症化リスク
初期症状
レプトスピラ症は、感染初期の軽い症状を見逃すと進行し、命に関わることもあります。早めに異変に気づくことが大切です。
- 食欲不振、発熱、元気がない
感染初期は、発熱や倦怠感が見られることが多く、食欲が落ちたり、散歩を嫌がったりすることがあります。
- 嘔吐・下痢、黄疸
胃腸の不調が現れることがあり、嘔吐や下痢が続くことも。さらに、肝臓がダメージを受けると、目の白目や皮膚が黄色くなる(黄疸)ことがあります。
- 腎臓や肝臓への影響
頻尿や尿の色が濃くなる、排尿回数が減るといった変化が見られることがあります。これらは腎機能の低下を示している可能性があり、放置すると脱水症状や腎不全につながることもあります。
重症化した場合の症状と合併症
レプトスピラ症が進行すると、多臓器に深刻な影響を及ぼし、致死率が高まるため、注意が必要です。
- 腎不全・肝不全を引き起こし致死率が高まる
感染が進むと腎臓や肝臓の機能が著しく低下し、毒素を排出できなくなることで命に関わる状態に。尿がほとんど出なくなったり、強い黄疸や意識低下が見られたら、すぐに獣医師の診察を受ける必要があります。
- 肺出血型レプトスピラ症
一部の犬では、レプトスピラ菌が肺の血管を破壊し、大量の出血を引き起こすことがあります。これは「肺出血型レプトスピラ症」と呼ばれ、急性の呼吸不全を引き起こし、数時間で命を落とすケースもあるため、非常に危険です。
人への感染リスク
レプトスピラ症は人畜共通感染症のため、飼い主にも感染するリスクがあります。犬の尿や体液を介して感染することが多いため、排泄物の処理時は手袋を着用し、手洗いを徹底することが重要です。また、飼い主自身が発熱や筋肉痛、倦怠感を感じた場合は、医療機関を受診することをおすすめします。

犬のレプトスピラ症を予防する方法
レプトスピラ症は、一度感染すると重症化するリスクがあるため、日常的な予防対策がとても大切です。特にワクチン接種や生活環境の管理によって、感染リスクを大きく減らすことができます。
ワクチン接種での予防
レプトスピラ症の予防には、ワクチン接種が最も有効な手段とされています。
- レプトスピラ症ワクチンの種類と接種頻度
レプトスピラ菌には複数の血清型があり、ワクチンには6種混合ワクチンや8種混合ワクチンが含まれています。一般的に、子犬は生後2~3ヶ月頃に初回接種し、その後毎年1回の追加接種(ブースター接種)が推奨されます。
- ワクチンの効果と持続期間
レプトスピラ症ワクチンは感染リスクを下げる効果がありますが、100%の予防ができるわけではありません。また、ワクチンの効果は約1年なので、定期的な接種が必要です。特にアウトドアや水辺で遊ぶ機会が多い犬は、毎年の接種を欠かさないようにしましょう。
- 副作用や接種時の注意点
一部の犬では、ワクチン接種後に軽い副作用(発熱や倦怠感)が見られることがあります。また、ごくまれにアレルギー反応が起こる可能性もあるため、接種後しばらくは様子を観察し、異変があればすぐに獣医師に相談しましょう。
日常生活でできる感染対策
ワクチンに加えて、日頃の生活環境を見直すことで、レプトスピラ症の感染リスクを大幅に減らすことができます。
- 汚染された水や泥に近づけない
レプトスピラ菌は川や池、水たまり、ぬかるみなどの湿った環境で生存しやすいため、雨上がりの散歩や水辺での遊びには注意が必要です。特に、野生動物が多いエリアでは、感染リスクが高まるため、できるだけ近づけないようにしましょう。
- ネズミ対策を徹底する
レプトスピラ症の主な感染源であるネズミの尿が庭や屋内に侵入しないよう、食べ物を放置しない、ゴミを適切に管理する、通り道を塞ぐなどの対策を行いましょう。ペットフードの保管も、密閉容器を使うことでネズミの侵入を防ぐことができます。
- 犬の体調管理を徹底する
免疫力が低下している犬ほど感染リスクが高くなるため、普段からバランスの取れた食事、適度な運動、ストレスの少ない環境を整えることが重要です。特に、高齢犬や持病のある犬は体力が落ちやすいため、定期的な健康チェックを欠かさないようにしましょう。
まとめ
犬のレプトスピラ症は、人にも感染する可能性がある危険な細菌感染症です。主な症状は発熱や食欲不振、腎不全・肝不全などの重篤な合併症につながることもあります。感染を防ぐには、ワクチン接種、汚染された水やネズミとの接触を避ける、愛犬の健康管理を徹底することが重要です。早期発見と適切な治療が鍵となるため、愛犬に異変を感じたらすぐに獣医師に相談しましょう。