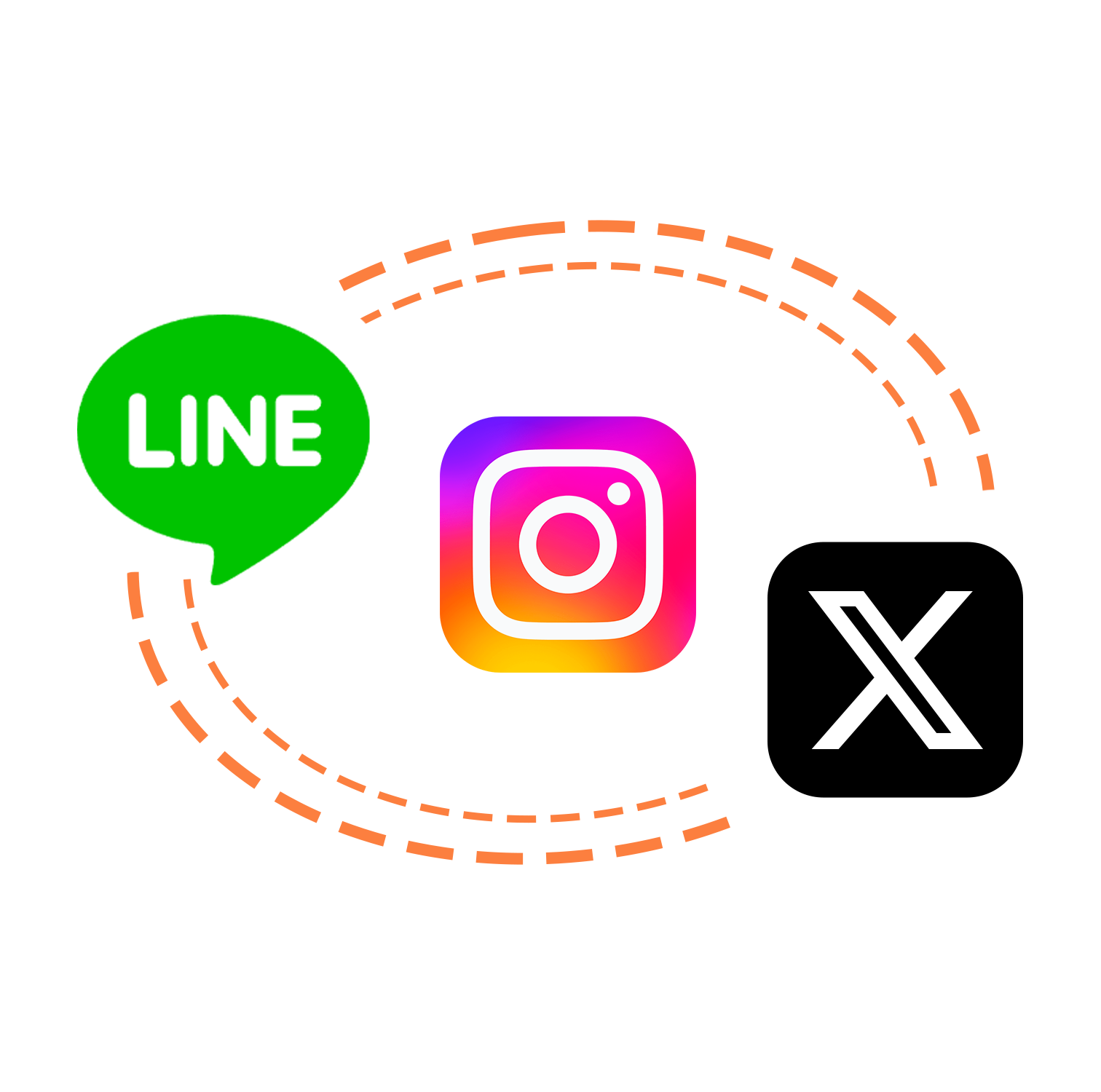PETTENA編集部は、ペットとその飼い主がより良い生活を送れるよう、専門的な知識に基づいた信頼性のある情報を提供するチームです。特に、ペットカートを中心に、安全で楽しいお出かけをサポートするコンテンツをお届けしています。
猫のくしゃみが止まらない!緊急度別受診目安と今すぐできる対処法|PETTENA
「クシュン、クシュン」——愛猫のくしゃみが続いていると、「ただのくしゃみ?」「病気のサイン?」と不安になりますよね。猫のくしゃみには、一時的な刺激によるものから、深刻な病気が隠れているケースまでさまざまな原因があります。この記事では、猫のくしゃみの原因、緊急度別の受診目安と、自宅でできる対処法をわかりやすく解説します。
猫がくしゃみをするのはどんなとき?

猫のくしゃみの仕組みと生理現象
猫のくしゃみは、人間と同様に鼻の粘膜が刺激された時に起こる生理現象です。鼻腔内に入った異物を排出するための自然な反応で、健康な猫でも1日に1-2回くしゃみをすることは珍しくありません。
生理的なくしゃみの特徴
・1回か2回で収まる
・頻度が少ない(1日1-2回程度)
・他の症状(鼻水、目やに等)を伴わない
・食欲や元気に変化がない
このような一時的なくしゃみであれば、特に心配する必要はないでしょう。
「たまに」と「連続」の違いが意味すること
たまにしかくしゃみをしない場合、多くのケースでは心配いりません。例えば、お部屋のほこりや猫砂の粉塵など、一時的な刺激に対する生理的な反応であることがほとんどです。
猫は人間よりも嗅覚が敏感なため、私たちが気付かないような微細な粒子にも反応することがあります。特に、新しい猫砂に変えた時や掃除をした直後など、環境の変化があった際に1~2回くしゃみをする程度であれば、自然な現象と言えるでしょう。
しかし、連続してくしゃみが続く場合や、1日に何度も繰り返す場合は注意が必要です。例えば「クシュン、クシュン」と5回以上続くようなケースでは、何らかの病気が潜んでいる可能性が高まります。
猫風邪などの感染症にかかっていると、くしゃみが頻発する傾向があり、次第に鼻水や目やになどの他の症状も現れてきます。特に子猫や老猫の場合、免疫力が弱いため症状が急変するリスクもあるため、早めの対応が求められます。
猫のくしゃみの主な原因と分類

感染症による猫のくしゃみ
猫のくしゃみで最も多い原因が、ウイルスや細菌による感染症です。
特に猫の風邪の症状では、頻繁なくしゃみが特徴的です。代表的な病原体として知られているのは、猫ヘルペスウイルス(FHV-1)と猫カリシウイルス(FCV)です。これらの感染症では、くしゃみに加えて鼻水や目やに、発熱などの症状を伴うことが多く、特に子猫や免疫力の低下した高齢猫では重症化するリスクがあります。
感染症によるくしゃみの特徴は、連続して何度も繰り返す点にあります。例えば「クシュン、クシュン」と5回以上続くようなケースでは、感染症を疑う必要があります。
また、鼻水の色も重要なサインで、透明なものから始まり、症状が進むと黄色や緑色の膿のような鼻水に変化していきます。このような症状が見られたら、早めに動物病院を受診することが大切です。
アレルギーやハウスダストが原因のくしゃみ
人間と同じように、猫もアレルギー反応でくしゃみをすることがあります。
主なアレルゲンとしては、ハウスダストやカビ、花粉、一部の食品などがあります。アレルギー性のくしゃみは季節によって変動する場合があり、例えば春先に症状が悪化するようであれば花粉アレルギーの可能性も考えられます。
アレルギーによるくしゃみの特徴は、特定の環境下で症状が出やすい点です。掃除をした直後や、カーペットの上を歩いた後などに頻繁にくしゃみをするようであれば、環境アレルギーを疑ってみる必要があります。
異物の混入や環境刺激によるくしゃみ
猫の鼻は非常に敏感で、ほこりや小さなごみなどの異物が入るだけでもくしゃみを引き起こします。
また、タバコの煙や強い芳香剤、香水などの化学物質も鼻の粘膜を刺激し、くしゃみの原因になります。このタイプのくしゃみは一時的なものが多く、異物が排出されれば通常はすぐに治まります。
環境刺激によるくしゃみの特徴は、単発的で短時間で収まる点です。ただし、異物が鼻腔に詰まったままになっていると、くしゃみが続くだけでなく、鼻血が出ることもあるので注意が必要です。
その他の疾患に伴うくしゃみ
慢性的なくしゃみが続く場合、より深刻な疾患が隠れている可能性があります。高齢猫では鼻腔内の腫瘍やポリープが原因でくしゃみが止まらなくなることがあります。このようなケースでは、くしゃみに加えて鼻血や顔の変形、食欲低下などの症状が現れることが特徴です。
また、歯周病が進行すると、口腔内の炎症が鼻腔にまで波及してくしゃみを引き起こすことがあります。特に、くしゃみと同時に口臭が気になる場合や、食事の際に痛がる様子が見られる場合は、歯科疾患を疑う必要があります。
これらの疾患が疑われる場合、早期に専門医の診断を受けることが重要です。
年齢や猫種によって異なるくしゃみの傾向

おすすめ記事:猫のご飯が足りないサインとは?1日の食事回数と量の目安をチェック
子猫・老猫がくしゃみに注意すべき理由
子猫と老猫は、免疫力の違いからくしゃみに対する注意が必要な年齢層です。
子猫の場合、免疫システムがまだ完全に発達していないため、一見軽そうなくしゃみでも、あっという間に重症化するリスクがあります。
特に生後6ヶ月未満の子猫が頻繁なくしゃみをしている場合、猫風邪に感染している可能性が高いでしょう。子猫のくしゃみに加えて、目やにや食欲不振が見られたら、24時間以内に動物病院を受診することが推奨されます。
一方、7歳以上のシニア猫では、加齢に伴う免疫力の低下がくしゃみの原因になることがあります。老猫のくしゃみで特に注意したいのは、慢性的な鼻炎や歯周病からの二次感染、そして腫瘍の可能性です。
高齢猫が1ヶ月以上続くくしゃみを示している場合、単なる風邪ではなく、より深刻な基礎疾患が隠れているかもしれません。
また、老猫は脱水症状を起こしやすいため、くしゃみで鼻が詰まると嗅覚が鈍り、食欲不振に陥る悪循環に注意が必要です。
短頭種に多い慢性くしゃみ
ペルシャやエキゾチックショートヘア、スコティッシュフォールドなどの鼻ぺちゃ猫は、その独特の頭部構造から慢性的なくしゃみに悩まされやすい傾向があります。
これらの猫種は鼻の穴が狭く、鼻涙管も曲がりくねっているため、分泌物が溜まりやすく、常に鼻が詰まったような状態になりがちです。特に季節の変わり目や湿度が変化する時期には、くしゃみが増える傾向があります。
猫のくしゃみに伴う危険サイン
鼻水・目やになどのチェックポイント
鼻水の状態
透明な鼻水が数日続く場合でも注意が必要ですが、特に黄色や緑色の膿のような鼻水は細菌感染の疑いがあります。
片方の鼻だけから出血を伴う鼻水が出る場合、異物や腫瘍の可能性も考えられます。鼻水が乾燥して鼻の周りにこびりついているのも、慢性化しているサインです。
目やにの特徴
目やにが黄色く粘り気のある場合や、量が明らかに増えている場合は感染症の可能性大です。まぶたが腫れていたり、目をしょぼしょぼさせていたりするのも危険信号です。
特に猫ヘルペスウイルスでは、角膜炎を併発することが多いため要注意です。
元気・食欲の変化
くしゃみに加えて遊ぶ時間が減った、名前を呼んでも反応が鈍いなどの変化は、体調不良を示しています。
食欲が普段の70%以下に低下している場合、早急な対応が必要です。特に水を飲む量が減っていると、脱水症状のリスクが高まります。
「すぐ病院へ行くべき症状」早見リスト
| 受診の目安 | 症状 |
| 夜間でも即受診 | ・口を開けた呼吸 ・鼻からの大量出血 ・24時間以上絶食 ・完全にぐったり ・歯茎が白/紫色 |
| 翌日までに受診 | ・3日以上黄色/緑色の鼻水 ・目やにで目が開かない ・食欲50%以下 ・くしゃみ+激しい咳 ・40℃以上の発 |
| 症状持続時受診 | ・透明鼻水 ・1日10回以上くしゃみ ・片鼻だけ鼻水 ・目やに増加 ・活動量低下 |
猫のくしゃみに潜む「逆くしゃみ」
猫の逆くしゃみとは?
猫の逆くしゃみは、正式には発作性呼吸と呼ばれる現象で、一見くしゃみのように見えますが、実は全く異なる呼吸器系の反応です。通常のくしゃみが鼻から勢いよく空気を出すのに対し、逆くしゃみは逆に鼻から空気を激しく吸い込む動作が特徴です。
猫が突然首を伸ばし、「フゴフゴ」「ブーブー」といった特徴的な音を立てながら、何かに詰まったような呼吸を始めます。発作は通常30秒から1分程度で自然に治まりますが、初めて見る飼い主さんは驚き、窒息していると勘違いすることも少なくありません。
通常のくしゃみとの違い
逆くしゃみと通常のくしゃみを見分けるポイントは、音と動作にあります。
通常のくしゃみは「クシュン!」という鋭い音とともに、頭を前にかがめるような動作を伴います。一方、逆くしゃみでは「ブーブー」「フゴフゴ」といった低く連続的な音がし、首を伸ばして胸を張るような姿勢をとります。
また、通常のくしゃみは1回か2回で終わることが多いのに対し、逆くしゃみは数十秒間続く発作的な症状が特徴です。
家庭でのくしゃみ対処法

空気の乾燥対策とおすすめ加湿器
猫のくしゃみ対策として、まず見直したいのが室内の湿度管理です。乾燥した空気は鼻の粘膜を刺激し、くしゃみを誘発します。理想的な湿度は50~60%で、特に冬場やエアコン使用時は注意が必要です。
加湿器を選ぶ際は、猫の安全性を第一に考えましょう。加湿器の水は毎日交換し、週に1度はクエン酸などで除菌洗浄を。
加湿器が難しい場合は、洗濯物を室内に干す、浴室のドアを開けておくなどの方法も有効です。
ハウスダスト・花粉対策の掃除法
効果的な掃除のポイントは上から下へ、乾燥拭きから湿り拭きへの順番です。まずはハンディモップで高い所のホコリを落とし、次にフローリング用の静電モップで床のホコリを除去。最後に微粒子までキャッチできるウェットシートで仕上げ拭きを。
掃除のタイミングは猫がリラックスしている時が最適です。掃除機の音が苦手な猫には、音の静かなサイクロン式がおすすめです。
花粉対策としては、帰宅時に猫用のウェットタオルで体を軽く拭いてあげると効果的です。
食事やサプリで免疫力を高める方法
免疫力を高める食事の基本は、良質なタンパク質と適度な水分補給です。ドライフードだけではなく、ウェットフードを組み合わせて水分摂取量を増やしましょう。
オメガ3脂肪酸(EPA/DHA)を含むサーモンオイルや、腸内環境を整える乳酸菌サプリも効果的です。
特にビタミンA・C・Eは粘膜を強化するので、くしゃみが気になる時期は意識して与えましょう。
猫のくしゃみを防ぐために飼い主ができること

ワクチン接種と定期健診の重要性
猫のくしゃみ予防において、ワクチン接種は最も効果的な手段の一つです。
特に猫風邪の原因となる猫ヘルペスウイルス(FHV-1)と猫カリシウイルス(FCV)に対するコアワクチンは、子猫の時期から適切なスケジュールで接種することが大切です。生後8週齢から2~4週間隔で計3回、その後は年1回の追加接種が推奨されています。
定期健診は年1回が基本ですが、7歳以上のシニア猫では半年に1回の受診が理想的です。健診時には、飼い主さんが気付きにくい初期の歯周病や鼻腔内の異常を発見できることもあります。
ストレスを減らす環境づくり
安心できる縦方向の空間構成
キャットタワーや棚を設置し、猫が高い場所から周囲を見渡せるようにしましょう。猫は身を隠せる場所があると安心します。段ボール箱や専用の隠れ家を用意してあげてください。
PETTENA Select 猫ベッド ステップ
¥4,980
¥4,980
適切なトイレ環境
トイレの数は「猫の頭数+1」が基本です。静かで落ち着ける場所に設置し、毎日清掃を。猫砂の種類は猫の好みに合わせて選びましょう。
遊びと休息のバランス
1日10~15分のインタラクティブプレイ(おもちゃを使った遊び)を2~3回行い、狩猟本能を満たしてあげましょう。遊んだ後は必ず休息時間を確保することが大切です。
食事環境の最適化
水飲み場は複数箇所に設置し、食事場所は静かで落ち着ける空間に。フードボウルは浅めの陶器製が理想的です。
環境変化への配慮
引っ越しや新しい家族の増加など、生活の変化がある時は特に注意が必要です。フェロモン製品を活用するなど、ストレス緩和に努めましょう。
猫のくしゃみに関すよくある質問
Q:猫がくしゃみをよくするんだけど、これって病気かも?
猫がたまに1〜2回くしゃみをするのは、ホコリや匂いが原因のこともあります。でも、くしゃみが何度も続いたり、鼻水や目やに、元気がないなどの症状があるときは、病気のサインかもしれません。そんなときは、早めに動物病院で診てもらうと安心ですよ。
Q:猫のくしゃみってストレスでも出るの?
猫も環境の変化や不安を感じると、免疫が下がってくしゃみが出やすくなることがあります。ストレスだけが原因とは限りませんが、体調を崩すきっかけになることも。引っ越しや家族の変化などがあったときは、猫の様子をよく見てあげてくださいね。
Q:猫風邪って放っておいても治る?
軽い猫風邪なら自然に回復することもありますが、放っておくと重症化したり慢性化することもあるんです。特に子猫やシニア猫は悪化しやすいので注意が必要です。くしゃみや鼻水が続くときは、無理させず早めに病院で診てもらうのがおすすめです。
Q:猫のくしゃみって、寒さが原因になることもある?
はい、寒さが原因でくしゃみをすることもあります。ただ、ホコリや花粉、風邪などほかの要因もあるので、「寒いだけ」と決めつけず、猫の体調や環境もあわせて見てあげることが大切です。
Q:猫風邪の薬ってどこで買えるの?
猫風邪のお薬は、基本的に市販されておらず、動物病院での診察を受けてから処方してもらう必要があります。自己判断で薬を与えず、獣医さんに相談するのが安心です。
まとめ
猫のくしゃみには、生理的なものから病気のサインまでさまざまな原因があります。特に連続して起こるくしゃみや鼻水・目やにを伴う場合は注意が必要です。緊急度を確認し、適切なタイミングで動物病院を受診しましょう。日頃から部屋の湿度管理や掃除を心がけ、愛猫が快適に過ごせる環境を整えることが予防につながります。気になる症状が続く場合は、早めに獣医師に相談してくださいね。