PETTENA編集部は、ペットとその飼い主がより良い生活を送れるよう、専門的な知識に基づいた信頼性のある情報を提供するチームです。特に、ペットカートを中心に、安全で楽しいお出かけをサポートするコンテンツをお届けしています。
猫を保護したらどうする?正しい対応と飼えない場合の対処法も解説|PETTENA
野良猫を保護したけど、どうすればいいかわからない…そんなお悩みはありませんか?この記事では、保護直後にすべき健康チェックから、飼えない場合の里親探しのコツまで、猫の命を守るための正しい手順を優しく解説します。
猫の保護を決める前に考えること

保護が本当に必要なケースとは?
この子、本当に保護が必要なのかな?と迷った時は、まず猫の状態をよく観察しましょう。明らかに痩せすぎていたり、ケガをしていたり、子猫で親猫の姿が見当たらない場合は、保護が必要な可能性が高いです。特に寒さの厳しい冬場や、交通量の多い場所にいる場合は、早めの判断が求められます。
一方で、毛艶が良くて適度にふっくらしている猫や、人慣れしていない成猫の場合は、地域猫としてそのまま見守る方が良い場合もあります。保護が必要かどうか迷った時は、地域の動物愛護団体や保健所に相談するのも一つの方法です。
迷い猫・地域猫との違い
迷い猫と地域猫の違いは、意外と見分けがつきにくいものです。
迷い猫は飼い主さんとはぐれてしまったペットで、人に慣れていることが多く、首輪やマイクロチップがついている場合もあります。
地域猫とは地域で管理されている野良猫のことで、耳先がV字にカットされているさくら耳が目印です。地域猫は不妊去勢手術済みで、地域の人々から餌をもらったり、一定の縄張りで生活しています。もしさくら耳の猫を見かけたら、保護する必要はありません。その子にとっては、今の環境が居場所なのです。
保護が向いていない人の特徴
猫が可愛いから…という気持ちだけで保護を決めるのは少し待ってください。猫の保護には、時間もお金もかかります。
保護に向いていないかもしれない方:
😺アレルギーがあるのに無理をしてしまう人
😺転勤が多く、住環境が変わりやすい人
😺経済的に余裕がなく、動物病院代を捻出できない人
😺我慢強さに欠け、猫の問題行動に対応できない人
😺家族や同居人の同意が得られていない人
😺アレルギーがあるのに無理をしてしまう人
😺転勤が多く、住環境が変わりやすい人
😺経済的に余裕がなく、動物病院代を捻出できない人
😺我慢強さに欠け、猫の問題行動に対応できない人
😺家族や同居人の同意が得られていない人
猫は10年以上生きることもありますので、ライフプランも考えた上で判断しましょう。一時預かりという選択肢もあるので、無理に引き取らなくても大丈夫です。
猫を保護する時の基本ステップ

捕獲方法と注意点
捕獲と聞くと大げさに感じますが、基本は猫にストレスを与えないことが大切です。
子猫の場合は、タオルで優しく包んで段ボールなどに入れましょう。成猫の場合は、ケガをしているなど緊急時でない限り、数日かけて餌付けしてから保護するのが理想的です。
動物病院で借りられる捕獲器を使うと安全です。無理に手で捕まえようとすると、猫も怖がりますし、引っかかれて感染症のリスクもあります。保護する時は厚手の手袋を着用し、長袖長ズボンで臨みましょう。特に野良猫はノミやダニがついていることが多いので、家に連れ帰った後の対策も忘れずに。
周囲の安全確保
保護作業中は、周りの安全にも気を配りたいものです。道路脇で保護する場合は、三角表示板を置くなどしてドライバーに知らせましょう。
また、猫が驚いて逃げ出さないよう、できるだけ静かな環境を作ることも大切です。夜間の保護は避け、明るい時間帯に行うのがベストです。住宅街では近所の方に一声かけておくと、誤解を防げます。
地域猫の場合は、地域の猫ボランティアさんに連絡を取るのもマナーです。保護後は、念のため近所に飼い主さんを探す張り紙をしたり、動物病院でマイクロチップの有無を確認してもらいましょう。
親猫・兄弟猫の有無確認
子猫を保護した時、すぐに連れ帰る前に周囲に親猫や兄弟猫がいないかを確認するクセをつけましょう。特に生後2ヶ月未満の子猫は、親猫が餌を探しに行っているだけかもしれません。1時間ほど離れた場所から観察したり、夕方まで待ってみるのも手です。
もし複数の子猫がいる場合は、可能な限り一緒に保護するのが理想的です。兄弟がいると社会化がスムーズになり、保護猫のストレスも軽減できます。どうしても一度に保護できない時は、その場所に目印をつけて後日また訪れるか、地域の猫サポート団体に連絡を取ると良いでしょう。
野良猫を保護した直後の対応

けが・ぐったりしている場合の応急処置
保護した猫がけがをしていたり、ぐったりしている場合、まずは落ち着いて状況を確認することが大切です。出血がある場合は清潔なガーゼやタオルで軽く押さえ、止血を試みましょう。ただし、強く押しすぎないように注意が必要です。
骨折が疑われる場合は、なるべく患部を動かさないようにし、段ボールなどで固定すると安心です。
目の前で事故に遭ったなど、明らかに重傷の場合は、すぐに動物病院へ向かいましょう。その際、猫の体を水平に保ち、なるべく振動を与えないように運ぶのがポイントです。
明らかな脱水や低体温への対処
子猫が冷たくなっている…そんな時は低体温症の可能性があります。特に子猫は体温調節が苦手なので、すぐに保温が必要です。ペットボトルにお湯を入れてタオルで巻き、猫の体に直接当たらないようにしながら温めてあげましょう。
脱水が疑われる場合は、スポイトで少しずつ水を与えますが、無理に飲ませると誤嚥の危険があるので要注意です。成猫の場合は、自分で飲める状態であれば、新鮮な水を用意してあげると良いでしょう。
いずれにしても、これらの症状が見られたら、なるべく早く獣医師の診察を受けることが重要です。
子猫・成猫別の食事
保護猫への食事は、年齢によって適切な方法が異なります。
生後1ヶ月未満の子猫には、猫用ミルクを人肌程度に温めて与えます。子猫用の哺乳瓶がない場合は、スポイトで少しずつ与えましょう。
固形フードが食べられる生後2ヶ月以降の子猫や成猫には、いきなりたくさん与えず、少量のふやかしフードから始めるのがおすすめです。特に長期間栄養不足だった猫は、急にたくさん食べると体に負担がかかるので、1日3~4回に分けて与えるようにしましょう。保護直後は消化の良い療法食が理想ですが、手元にない場合は鶏のささみの茹でたものなどでも代用可能です。
※北海道を拠点に犬猫の保護・譲渡活動を続けている認定NPO法人HOKKAIDOしっぽの会では、広大な地域をフィールドに、多くの命を救う取り組みを行っています。不妊手術の助成や行政との連携による啓蒙活動にも力を入れ、“人と動物が共生する幸せな社会”の実現を目指して日々奮闘されています。
現在、医療費や運営費の高騰、施設の老朽化など厳しい状況が続いている中で、こうした活動を支えるためのご寄付を広く呼びかけています。もし「なにか力になりたい」と思われた方がいらっしゃいましたら、しっぽの会の活動にご参加いただけると嬉しいです。

現在、医療費や運営費の高騰、施設の老朽化など厳しい状況が続いている中で、こうした活動を支えるためのご寄付を広く呼びかけています。もし「なにか力になりたい」と思われた方がいらっしゃいましたら、しっぽの会の活動にご参加いただけると嬉しいです。

医療の充実と飼育環境を整備し、より多くの犬猫の命を繋ぎたい
保護直後のお風呂がNGな理由
ノミやダニが心配だから、保護したばかりの猫をお風呂に入れたくなる気持ちはわかりますが、これは逆効果です。
保護直後の猫は強いストレスを感じており、お風呂はさらに体力を消耗させる行為です。また、低体温のリスクもあるため、基本的にはタオルで軽く拭く程度に留めましょう。ノミが気になる場合は、獣医師が推奨するスポットタイプの駆除薬を使うか、櫛で丁寧にとる方法が安全です。
どうしても洗う必要がある場合は、体調が安定してから、猫用シャンプーを使って短時間で済ませるようにしましょう。
すぐにできない時の応急対応

動物病院にすぐ行けない時にできること
夜間や休日で動物病院が開いていない時は、まず安静と保温を最優先にしましょう。
段ボールやキャリーケースに清潔なタオルを敷き、静かで暖かい場所に置きます。猫が怖がらないよう、周りをタオルで覆って暗くするのもおすすめです。脱水が心配な場合は、経口補水液を薄めたものを少量ずつ与え、嘔吐がないか注意深く観察しましょう。
ただし、けいれんを起こしている場合や、明らかに苦しそうな時は、夜間救急病院を探すことを優先してください。
一時的な居場所の作り方
😺高さのある段ボールや洗濯かごを使い、逃げ出せないようにする
😺床には吸水性の良いペットシーツを敷く
😺寒さ対策として湯たんぽやペットヒーターを設置
😺トイレは浅めの容器に猫砂を入れた簡易的なものでOK
😺水飲み場はひっくり返さないように重い容器を使う
😺高さのある段ボールや洗濯かごを使い、逃げ出せないようにする
😺床には吸水性の良いペットシーツを敷く
😺寒さ対策として湯たんぽやペットヒーターを設置
😺トイレは浅めの容器に猫砂を入れた簡易的なものでOK
😺水飲み場はひっくり返さないように重い容器を使う
特に子猫の場合は、狭くて暗い場所を好むので、タオルで覆いを作ってあげると落ち着きます。成猫の場合は、できるだけ広い空間を確保し、隠れられる場所を用意してあげましょう。
応急処置チェックリスト
いざという時に慌てないよう、以下のチェックリストを参考にしてください。
体温確認
猫の平熱は38~39度程度と人間より少し高めです。耳や肉球が冷たい場合は、湯たんぽやペットボトルにお湯を入れてタオルで包んだものでゆっくり温めてあげます。特に子猫の場合、低体温は命に関わるので要注意です。逆に熱すぎる場合も発熱の可能性があるので、なるべく早く動物病院に連れて行きましょう。
呼吸状態
正常な猫の呼吸数は1分間に20~30回程度です。呼吸が荒かったり、口を開けて苦しそうにしていたりしないか観察します。呼吸時にゼーゼーという音がする、胸が大きく波打つように動いているなどの異常が見られたら、すぐに獣医師の診察が必要です。呼吸状態を確認する時は、猫をなるべく刺激しないよう、少し離れた位置から静かに観察しましょう。
目や鼻の分泌物
健康な猫の目はきれいで、鼻も湿り気があります。目やにが大量に出ていたり、黄色や緑色の鼻水が出ている場合は感染症の可能性があります。片目だけに異常がある場合はけがの可能性もあります。分泌物の状態はスマホで写真に撮っておくと、後で動物病院で説明する時に便利です。ただし、無理に目を開けようとすると猫にストレスを与えるので、自然に出てくる分泌物を観察する程度にしましょう。
けいれんやふらつきの有無
猫がけいれんを起こしていたり、歩く時にふらついていたりしないか注意深く見ます。神経症状が出ている場合は、中毒や脳の障害など重篤な状態の可能性があります。このような症状が見られたら、すぐに動物病院へ。
移動中はキャリーケースを大きく揺らさないようにし、けいれんの様子を動画に記録しておくと診断の助けになります。
食欲・水分摂取の状態
保護直後の猫はストレスで食事を摂らないこともありますが、24時間以上何も食べない・飲まない場合は危険信号です。
子猫の場合は特に、低血糖になりやすいので注意が必要です。無理に食べさせようとせず、香りの強いウェットフードや猫用ミルクを少量ずつ試してみましょう。水分摂取が確認できない場合は、スポイトで少しずつ水を与えますが、誤嚥しないよう慎重に行ってください。
排泄の有無
トイレの状態も健康のバロメーターです。下痢や血便、血尿がないか確認しましょう。特に子猫の場合は、親猫が排泄を促す役割を果たしているため、保護したばかりの子猫は排泄できないことがあります。温めた濡れタオルで優しく肛門周辺を刺激してあげると、排泄を促すことができます。成猫の場合は、トイレを我慢してしまうこともあるので、落ち着いた環境でトイレを用意してあげましょう。
体表面のけがや腫れの確認
毛を優しくかき分けて、皮膚の状態を確認します。外傷や腫れ、しこりがないか、毛が抜けている部分はないかをチェックします。触ると痛がる場所がないかも注意深く観察しましょう。長毛種の場合は特に、毛の下にけがが隠れていることがあるので、入念に確認する必要があります。
ノミ・ダニのチェック
耳の裏や首周り、お腹など、ノミやダニが寄生しやすい場所を重点的に確認します。ノミがいると黒い粒が見つかることが多く、ダニは皮膚に食い込んでいるのが確認できます。
保護直後は駆除薬を使う前に動物病院で診てもらうのが理想ですが、どうしてもすぐに対処が必要な場合は、猫用のノミ取り櫛を使って丁寧にとる方法があります。ただし、無理に引き剥がそうとすると皮膚を傷つけるので注意が必要です。
これらの項目をメモしておくと、後で動物病院に行った時にスムーズに状況を伝えられます。スマホで写真や動画を撮っておくのもおすすめです。
動物病院での初期対応と検査
必要な検査と費用感
保護猫を初めて動物病院に連れて行く時は、どのような検査が必要なのか気になりますよね。
基本的には健康診断セットとして、以下の検査が推奨されます。
| 検査項目 | 目的 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 身体検査 | 全身の健康状態を確認 | 2,000~3,000円 |
| 糞便検査 | 寄生虫の有無をチェック | 1,500~2,500円 |
| 血液検査 | 内臓機能や感染症の確認 | 3,000~5,000円 |
| FIV/FeLV検査 | 猫エイズ・白血病ウイルスの検出 | 4,000~6,000円 |
| 耳垢検査 | 外耳炎や感染のチェック | 1,000円前後 |
地域や病院によって費用は異なりますが、初診で15,000円程度を見ておくと安心です。特に子猫の場合は、回虫やノミの駆除が必要なケースが多いので、追加費用も考慮しましょう。動物病院によっては保護猫割引を設けているところもあるので、事前に問い合わせてみるのもおすすめです。
ワクチン・寄生虫対策
ワクチン接種は、猫の年齢や健康状態にもよりますが、保護後2週間ほど経って体調が安定してから開始するのが一般的です。混合ワクチン(3種~5種)は初年度は2~4週間隔で2回接種し、その後は年1回の追加接種が必要です。費用は1回あたり4,000~6,000円程度。
寄生虫対策は、保護直後から始めましょう。ノミ・ダニ駆除薬(スポットタイプ)は体重に合わせて月1回、回虫などの内部寄生虫には経口薬を使用します。特に外で保護した猫は、ほぼ100%何らかの寄生虫を持っていると考えた方が良いでしょう。駆除薬は動物病院で処方してもらうのが最も安全です。
不妊手術のタイミング
不妊手術(避妊・去勢)は、生後6ヶ月前後が一般的な時期です。ただし、保護猫の場合は正確な年齢がわからないことも多いので、体重が2kg以上あることと、体調が安定していることを目安にしましょう。
地域猫として保護した場合は、自治体の補助制度を活用できる場合もありますので、事前に確認してください。
自宅での環境整備と準備
最低限必要なグッズ
保護猫を迎える際に揃えておきたい基本グッズは以下の通りです。
😺浅めのトイレ
😺粒が細かい猫砂
😺陶器かステンレス製食器
😺通院用キャリーケース
😺ベッドorタオル
😺爪とぎ
😺年齢に合ったフード
😺粒が細かい猫砂
😺陶器かステンレス製食器
😺通院用キャリーケース
😺ベッドorタオル
😺爪とぎ
😺年齢に合ったフード
最初から高価なものを揃える必要はありません。100円ショップでも手に入るアイテムで十分対応できます。特に保護直後は、猫が落ち着くまで環境を変えないことが大切なので、シンプルなセットから始めましょう。
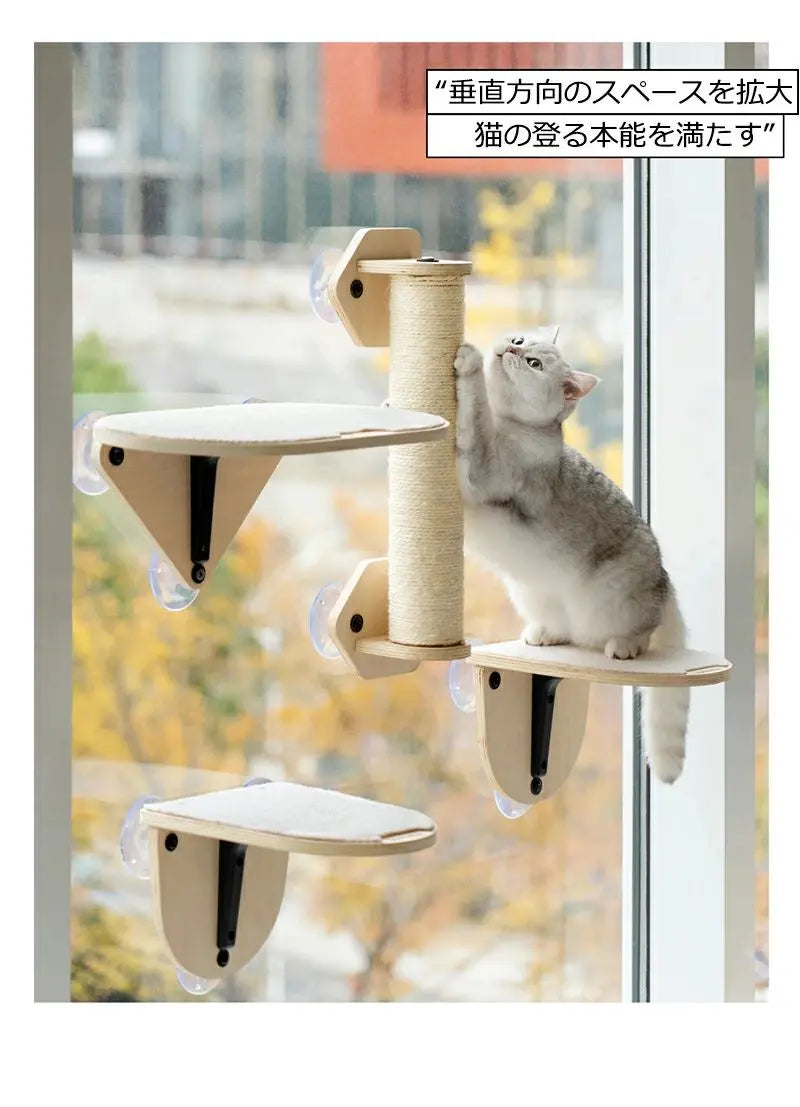
PETTENAスタッフ厳選|大切な家族のために、本当に“いいもの”だけを!
PETTENAのスタッフがひとつひとつ丁寧に選び抜いた、こだわりのペット用品を集めました。
PETTENAのスタッフがひとつひとつ丁寧に選び抜いた、こだわりのペット用品を集めました。
トイレトレーニングのコツ
保護猫のトイレトレーニングで重要なのは失敗を叱らないことです。自然とトイレを覚える猫も多いですが、以下のポイントを押さえると成功率が上がります。
😺トイレは食事場所から離して、静かで落ち着ける場所に設置
😺猫が床の匂いを嗅いでそわそわし始めたらトイレに連れて行く
😺最初は2~3時間ごとにトイレに誘導
😺成功したらおやつなどで大げさに褒めて
😺失敗しても絶対に叱らず、臭いを完全に消去
😺猫が床の匂いを嗅いでそわそわし始めたらトイレに連れて行く
😺最初は2~3時間ごとにトイレに誘導
😺成功したらおやつなどで大げさに褒めて
😺失敗しても絶対に叱らず、臭いを完全に消去
特に外で保護した成猫は、最初は屋外でしか排泄できないこともあります。焦らず根気よく、猫のペースに合わせてトレーニングしましょう。どうしてもうまくいかない場合は、トイレの形状や猫砂の種類を変えてみるのも一つの方法です。
感染症予防と隔離期間について
保護猫を迎える際、すでに他の猫がいるご家庭では、2週間程度の隔離期間を設けることが重要です。猫風邪や猫エイズなど、感染力の強い病気を持っている可能性があるためです。
隔離中は世話をする人が触れた後は必ず手洗いをし、衣類も着替えるとなお安心です。新しい猫の健康状態が安定し、動物病院で問題ないと診断されてから、ゆっくりと他の猫と対面させるようにしましょう。
飼うかどうか決める時の判断基準

家族全員の同意があるか
猫を飼いたい!という気持ちが先走る前に、まずはご家族全員としっかり話し合うことが大切です。
特に小さなお子さんや高齢のご家族がいる場合、アレルギーの有無を確認する必要があります。猫アレルギーは実際に猫と接してみないと分からないことも多いので、可能であれば保護猫カフェなどでアレルギーテストをしてみるのがおすすめです。また、集合住宅にお住まいの場合は、管理規約でペット飼育が許可されているかも確認しましょう。
猫が来たら家が汚れるかもと心配される家族には、最近の猫トイレの性能の高さや、しつけの方法を具体的に説明すると理解を得やすくなります。
先住猫との相性
すでに猫を飼っているご家庭で新たに保護猫を迎える場合、相性問題は避けて通れません。
理想的なのは、年齢や性格が近い猫同士をマッチングさせることです。例えば、シニア猫に子猫を迎えるとストレスになるケースもあります。まずは1~2週間完全に隔離した状態でにおいを慣らし合い、ケージ越しに対面させるなど、段階を踏んで交流を深めましょう。
どうしても相性が悪い場合は、別々の部屋で飼育する選択肢もありますが、その分のスペースと世話の時間が必要になります。
経済的・時間的な余裕
猫を飼うには、初期費用で5~10万円、年間維持費で15~20万円程度かかると想定しておきましょう。特に注意したいのが想定外の医療費です。10年以上生きる猫の場合、シニア期になると病気の治療費がかさむことも少なくありません。ペット保険への加入を検討するのも一つの方法です。
時間的余裕も重要で、単身赴任や転勤が多い方には不向きかもしれません。猫は環境の変化に弱く、毎日のお世話や遊びの時間も必要です。旅行に行けなくなるかもという心配がある方は、信頼できるペットシッターや預かり施設を事前にリサーチしておくと安心です。
もし飼えない場合の選択肢

里親探しの方法と注意点
保護した猫を飼えなくなった場合、里親探しは責任を持って行いたいものです。まずは身近な知人や職場の同僚など、直接会える範囲で探してみましょう。その際には相手の飼育環境、家族の同意、経済状況、飼育経験などの情報を確認すれば安心です。
SNSで募集する場合は、個人情報保護の観点から、直接自宅住所を公開しないように注意が必要です。また、最近問題になっているペット転売を防ぐため、必ず5,000~10,000円程度の有償譲渡にし、譲渡契約書を交わすのが理想的です。
保護団体との連携方法
保護団体によっては、一時預かりを引き受けてくれたり、里親探しをサポートしてくれる場合があります。連絡する際は、猫の年齢・性別・性格・健康状態などの基本情報を正確に伝え、保護時の状況も詳しく説明しましょう。
ただし、すべての団体が余裕があるわけではないので、すぐに引き取ってもらえないこともあります。その場合は自分で面倒を見ながら、団体のサポートを受けて里親を探すというスタンスで臨むと良いでしょう。団体によっては、不妊手術費用の補助や、譲渡会の場を提供してくれることもあります。
SNSや譲渡会の活用術
SNSを活用する場合、TwitterやInstagramより、Facebookの保護猫専門グループや猫の里親募集サイトの方が効果的です。投稿する写真は、猫の魅力が伝わるよう、明るい自然光の下で撮影しましょう。
プロフィールの情報:
😺推定年齢・性別
😺性格(人懐っこい、大人しいなど)
😺健康状態(ワクチン接種済みか)
😺特記事項(他の猫と仲良くできるか等)
😺推定年齢・性別
😺性格(人懐っこい、大人しいなど)
😺健康状態(ワクチン接種済みか)
😺特記事項(他の猫と仲良くできるか等)
譲渡会に参加する場合は、猫をきれいにグルーミングし、人慣れさせておくことが大切です。会場では猫のストレスを考慮し、ケージをタオルで覆うなどの配慮を。最近ではオンライン譲渡会も増えているので、遠方の方にも門戸を広げられます。いずれの方法でも、譲渡後も数ヶ月はアフターフォローを続け、必要に応じてアドバイスできる関係を作っておくと安心です。
よくある質問
Q:猫を保護したら、最初に何をすればいいの?
まずは猫の体調をよく観察しましょう。けがをしていたり、ぐったりしている場合は無理に触らず、できるだけ早く動物病院へ。元気そうでも、ノミや病気の心配があるので、しばらくは他の動物と離して静かな場所で休ませてあげてくださいね。
Q:野良猫を保護したけど、どうしても飼えない…どうしたらいい?
まずは一時的に安全な場所を確保してあげてください。そのうえで、動物病院で健康チェックを済ませてから、里親探しを始めましょう。信頼できる保護団体やSNS、譲渡サイトなどを活用すると、よい出会いにつながることがありますよ。
Q:保護した猫って、すぐにお風呂に入れても大丈夫?
保護直後のお風呂はおすすめできません。知らない場所や人に囲まれて、猫はとても不安な状態ですし、体調が不安定なこともあります。まずは安心できる環境で休ませて、必要なら動物病院でシャンプーのタイミングを相談しましょう。
まとめ
保護した猫と幸せに暮らすためには、まず健康チェックと動物病院での検診が大切です。飼えない場合も、里親探しや保護団体との連携など、猫のためにできる選択肢があります。この記事で学んだことを活かせば、あなたもきっと猫の命を守るヒーローになれますよ。










































